ブータンのティンレイ元首相との対話
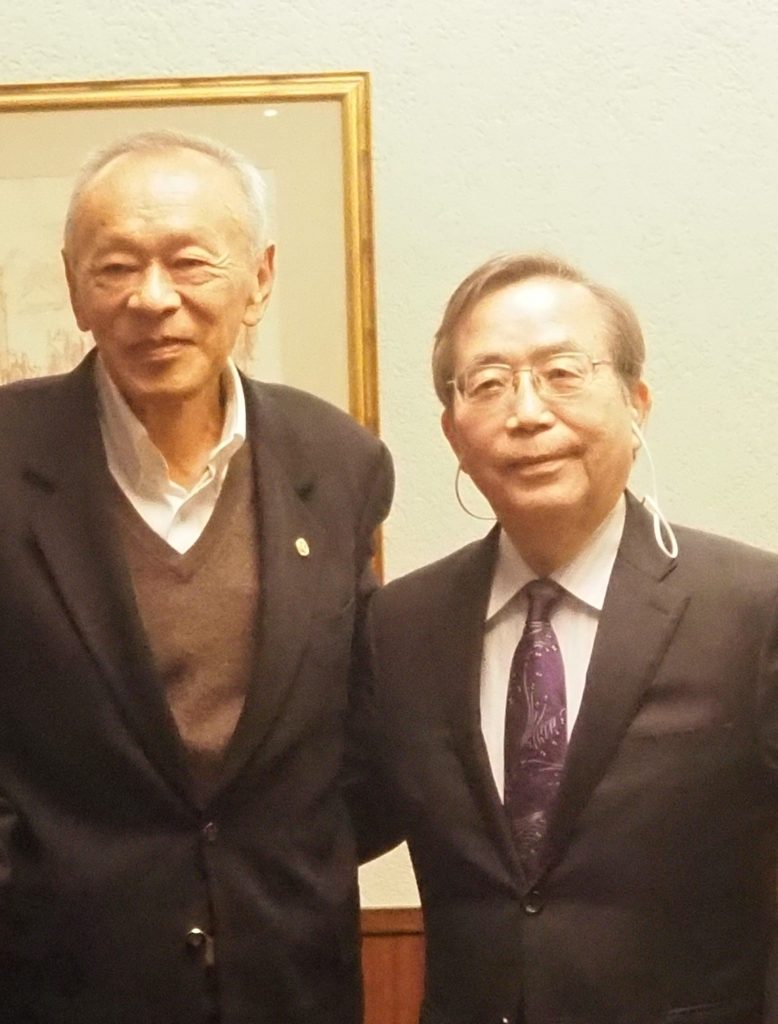
ティンレイ元首相と筆者=2025年3月、松下氏提供
ブータン王国のティンレイ元首相が去る3月上旬に来日され、お話をする機会がありました。以下は、筆者らがティンレイ元首相と3月6日の午後に懇談した際の対話をもとに取りまとめたものです。
ティンレイ元首相は、2008年から2013年までブータンの憲法制定後の普通選挙で選ばれた最初の首相として5年間務めました(憲法制定以前にも2回にわたり首相を務めています)。第4代ワンチュク国王が提唱したブータンのGNH(国民総幸福量、国の統治の目標に経済成長よりも国民の幸福の向上を掲げる)の思想を、国の発展の哲学、経済理論、そして行政の実際的な枠組みとして構築し、国際的にもその理念を広めることに多大な貢献をしています。
今回は3月5日に東京で開かれた「水と災害に関する国際シンポジウム」にパネリストとして招待され来日し、ご臨席された天皇陛下とも懇談をされています。
このシンポジウムでは、水と災害に関するさまざまな課題が議論されましたが、ティンレイ元首相は、とりわけブータンでの気候変動の影響を懸念しています。気候変動の被害では、太平洋の小島嶼国の海面上昇による国土の水没などが注目されますが、第三の極地と言われるヒマラヤ山脈の麓に位置するブータンも気候変動の影響に極めて脆弱です。多くの氷河湖を抱え、その崩壊による洪水被害が懸念されています。
ブータンは2009年にデンマークのコペンハーゲンで開催された気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)で、国として未来永劫に「カーボンネガティブ」(国全体の温室効果ガス(GHG)吸収量の方が排出量より大きい)を維持することを宣言しています。ブータンは豊かな森林に覆われた山国で、人口や経済活動も相対的に小さく、「カーボンネガティブ」が維持されている世界でも珍しい国です。憲法では国土の60%以上の森林を維持することが規定されており、一時減少してしまった森林面積を現在では70%以上に増やしています。小さな国であっても脱炭素型経済発展と国民の幸福向上のモデルを世界に示したいとの高い志を持っているのです。
ただし現実には、ブータンも多くの課題に直面しています。ブータンの主要な外貨収入は、水力発電による電力の売電と観光収入です。ところがコロナ禍により国を閉ざすことを余儀なくされ、しばらく観光客ゼロの状態が続きました。コロナ禍収束後、2022年9月から国を開放し、観光客を再び受け入れていますが、コロナ禍前の水準には戻っていません。
ブータンの観光政策は、少人数の観光客を受け入れ、質の高い長期滞在型で環境に配慮した観光をしてもらう、「高品質な旅を少数の人に」(high value, low volume)を旨としています。その手段として従来から1日当たり65ドルの観光税を徴収していました。コロナ禍後、これが200ドルに引き上げられましたが、その後100ドルに下げています。理想とする観光政策の実現に模索が続いています。

ブータンの棚田=松下氏提供
一方、多くの若者たちが海外、とりわけオーストラリアに移住していることも問題となっています。ブータンでは教育費は無料で、初等教育からほぼすべての科目が原則英語で教えられています。その成果として大学などの高等教育を修了した若者が増えていますが、彼らに適切な就職先を確保することが大きな課題です。
ブータンは国全体としては依然として自給自足型の農業に依存した経済が中心ですが、若者たちは農業をやりたがらない傾向があります。日本の技術協力の成果もあり、ブータンの農業生産力は向上していますが、食料自給率は依然として低いままです。水不足や野生生物による農業被害もあり、食料安全保障が重要な課題となっています。ブータンの人たちは仏教への信仰が厚く、野生生物を殺すことをしません。日本でも野生生物による農業被害が問題となっているので、この分野での日本とブータンとの経験や技術の交流が望まれます。
ワンチュク現国王は、2023年12月に、ブータン南部の町ゲレフーに位置する新たな経済拠点、ゲレフー・マインドフルネス・シティ(GMC)に関するビジョンを発表しました。これはブータンの文化、GNHの原則、精神的遺産に基づき、グリーンテクノロジー、教育、インフラへの投資を通じて、国の将来の成長の基礎を築き、国民に経済的機会を創出することを目指す開発です。この開発計画が実際にGNHの理念に沿い、カーボンネガティブを維持した脱炭素型発展のモデルとなりうるか、今後の進展が注目されます。
最後に私たちはティンレイ元首相に「ブータンにおけるGNHを基軸とした政策の進展状況をどう評価するか。」と聞きました。
その答えは以下のようなものでした。
「GNHの概念への理解は広がった。ただ、それがどこまで現実の政策を変え、社会の変革につながったかどうかについては道半ばだ。しかし希望はある。ブータンの人々の精神性、自発性、慈善への意識は高い。ブータンの人々の意識は世界の物質的な消費文明にさらされてもそう変わっていない。自然への畏敬、気候変動の脅威への理解も高まっている。例えばブータン人の25%は菜食主義者(vegetarian)である。その背景には肉食は環境への負荷が大きく、気候変動への影響があることの理解が広まっているからだ。世界は依然としてGDP至上主義の経済と政治が続いている。地球の限界を考えると、無限の物的経済成長の拡大を続けることは不可能だ。国民の幸福を政治の目的とするGNHの意義は今こそ認識されるべきである。」
ティンレイ首相は終始とても穏やかに語られましたが、その中にも、GNHへの強い思いが感じられる午後のひと時でした。
(松下和夫 京都大学名誉教授、(公財)地球環境戦略研究機関シニアフェロー)

