COP 16で生物多様性クレジット枠組み公表~オフセットは地域コミュニティが鍵か

熱気あふれるIAPBフレームワーク発表のイベント会場=原口真氏提供
コロンビア共和国・カリで、昨年開催された生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)。この会議に合わせて、「生物多様性クレジットに関する国際諮問委員会」(IAPB)が「高い完全性を備えた生物多様性クレジット市場のための枠組」を公表した。日本国内でも早急に議論を深める必要がある。
生物多様性のオフセットとは、その場の配慮でクリアできない課題を別の場所で埋め合わせること。クレジット市場は生物多様性という、地域固有でかつグローバルな意味も持つ自然資本の損失に歯止めをかけ、回復に転じるネイチャーポジティブの実現に期待されるメカニズムだ。しかし一方で、貴重な自然の破壊を助長する見せかけの環境配慮、グリーンウォッシュにつながるという危惧も根強い。前回のモントリオールのCOP15(2022年)の際にはカナダのトルドー首相が懸念を表明している。
IAPBは25カ国を超える120人以上で構成され、IUCN(国際自然保護連合)ラザン・アル・ムバラク会長も含む、金融、先住民族、地域コミュニティ、企業、学界、NGOなどが参加する。この1年以上、特に「高い完全性」について議論が進められ、公表に至った。
「高い完全性」の担保のために、①科学的根拠に基づくこと、②生物多様性の影響が及ぶ地域内でオフセットすることをはじめ国境を越えたオフセットや2次市場は認めない、③場所によって異なる生物多様性を念頭に標準化した測定の単位を定めない、などが盛り込まれている。また、自然の目標へのエビデンスに基づく貢献、生物多様性への影響の地域補償(厳格な基準に基づく)、購入者のサプライチェーン内での積極的な投資、というクレジットの使用目的も明記している。
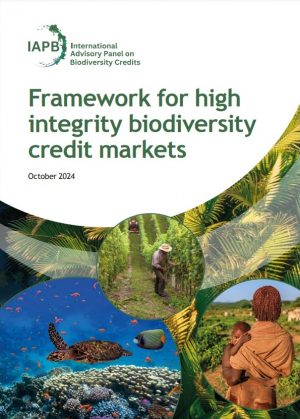
IAPBが公表した報告書 “Framework for high integrity biodiversity credit markets © 2024”の表紙。https://www.iapbiocredits.org/frameworkより
なお、今回のCOP16本体は日本のマスコミにはほとんど無視された感がある。実質的にネイチャーポジティブを含む「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(KMGBF)の採決が華々しく報道されたCOP15と対照的だ。それもそのはず、COPのハイレベルセグメントに日本から出席したのは大臣ではなく審議官だった。特に、生物多様性保全のための資源、資金の動員をめぐる議論が難航していて、COP15で合意された「昆明・モントリール生物多様性枠組」の達成を妨げるリスクを懸念する向きもある。
だが環境省によれば、会議の参加人数は13,000人と過去最大規模のCOPだったし、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への関心からか、日本から多数の企業経営層が参加した。また、議長国であるコロンビアの意向により、世界各地から先住民や女性、若者、地域など多様なコミュニティの声が集められ、「先住民及び地域社会の参画に関する補助機関」の設置が決議された。これは、日本にとっても、生物多様性クレジット市場にとっても注目される。
なぜなら、地域社会の重視は2010年のCOP10を契機に始まったSATOYAMAイニシアティブの更なる展開の契機になることが期待されるだけではない。今回公表された生物多様性クレジット市場の枠組みでも、地域住民(ローカル・コミュニティ)が重要なステークホルダーと位置づけられているからだ。COPで議論されている先住民といえば、日本ではアイヌ民族を思ってしまいやすいが、日本ではむしろ里地里山の担い手と考えるべきではないだろうか。地域の自然資源の持続可能な利用と、結果としての豊かな「生物文化多様性」を育んできた人々である。
かつて、世界に先駆けて環境影響評価制度が法制化されたアメリカでは、1990年代に開発時に失われる湿地自然環境の保全措置にノーネットロス(総量として水準を維持)が掲げられ、オフセットのためのミティゲーション・バンクが発足。その後、絶滅危惧種の生息環境のクレジット市場であるコンサベーション・バンクも展開している。
そしてネイチャーポジティブが国際目標となった現在、英国イングランドではノーネットロスを超えて生物多様性ネットゲイン(純増)政策が推し進められている。2024年からは開発時に10%のネットゲインが義務化された。その計算に用いる生物多様性のユニットは、特色、状態、戦略的意義の3要素で評価する。この手法は、検証を踏まえながら頻繁にバージョンアップされている。
さて、日本でも過去数回挫折したオフセットの議論だが、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」(環境省・農水省・国交省・経産省2024)でも、「各場所の自然資本は唯一無二であるため、ある場所における影響を他の場所の回復等で真に相殺することはできない」という文言が入っている。確かに、「真に」相殺は原理的に不可能でも、有意義なネットゲインに貢献する「高い完全性」を備えたクレジットの枠組みを検討する好機ではないだろうか。来年度から法制化される自然共生サイト認定にも追い風となる。
幸い、自然共生サイトやTNFDに企業の関心が高い。例えば、ネイチャーポジティブに向けて、これらの動きを流域など比較的まとまったランドスケープを単位に開発と保全・再生の事業が連携し、整理して、地域コミュニティに受け入れられるネットゲインの事例を示していくことから始められないだろうか。SATOYAMAイニシアティブを主導した日本から「高い完全性」の内容を発信していく好機となろう。
(森本幸裕・京都大学名誉教授・(公財)京都市都市緑化協会理事長)

